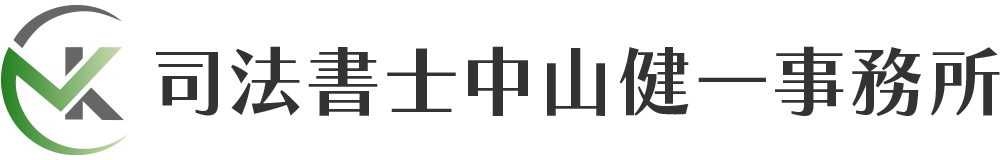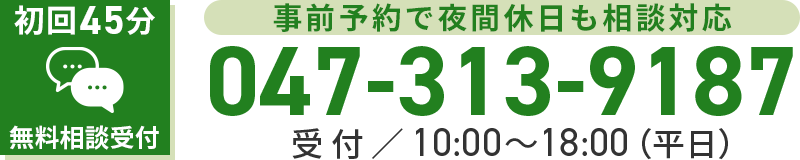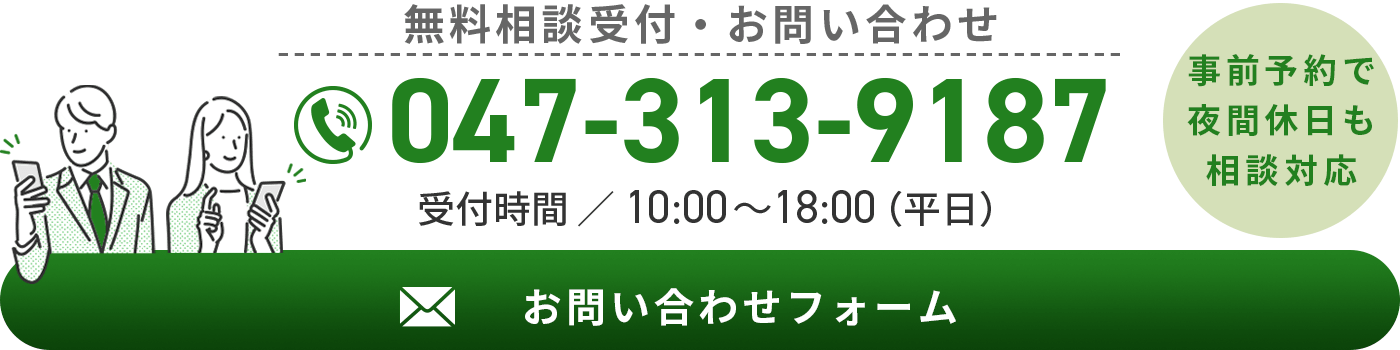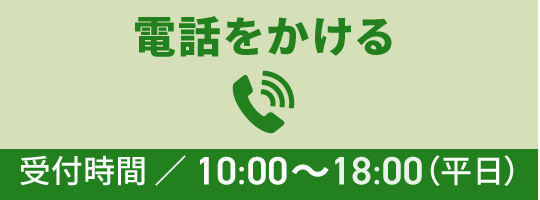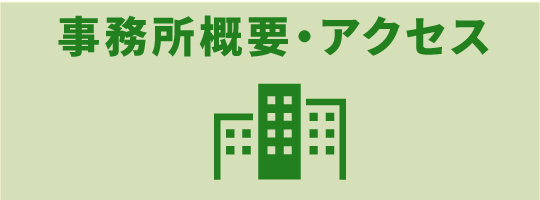相続放棄とは、被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も引き継がないという意思表示です。主に遺産に借金などマイナスの財産が多い場合に活用します。相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることによって行います。
原則、この3か月の期間を過ぎると、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
このページでは、相続放棄の流れや注意点について説明していきます。
このページの目次
相続放棄の流れ
提出先の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
代表的な必要書類
- 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 申述人1人につき800円の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
相続放棄をするときの注意点
相続放棄には3か月の期限がある
相続放棄をするには、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内にしなくてはなりません。この期間のことを熟慮期間と言います。
3か月の熟慮期間を超えた場合、事情によっては相続放棄が認められる場合もありますが、相続放棄が認められるか否かは家庭裁判所の裁量によります。相続放棄を検討されている方は、なるべく早く手続きをしましょう。
相続放棄が出来なくなる行為がある
相続財産を処分したり、隠匿や消費してしまうと、相続財産を認めた(=単純承認)ことになり相続放棄ができなくなります。安易な気持ちで相続財産に関わると、単純承認に該当する可能性があるので注意しましょう。
具体的にどのような行為が単純承認に該当するかはこちらのページをご覧ください。
相続放棄をすると撤回できない
家庭裁判所に相続放棄が認められると、原則として撤回はできません。相続放棄をした後、プラスの相続財産があることが分かった場合でも撤回はできないので、家庭裁判所に相続放棄の申述をする前に、相続財産の調査を行いましょう。
熟慮期間内に相続財産を把握できないことが想定される場合は、熟慮期間の伸長を申立てることもできます。熟慮期間の伸長についてはこちらのページをご覧ください。
3か月の熟慮期間を超えてしまった場合
繰り返しになりますが、相続放棄は自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
では、被相続人に借金がないと思っていたところ、3か月経過後に借金の督促が来た場合はどうなるのでしょうか。
このようなケースでは、借金の督促が来てから3か月以内に相続放棄の申述をすれば、相続放棄が認められる可能性はあります。
その際、なぜ相続開始から3か月経過後に相続放棄をすることになったのかの事情を説明した上申書を提出する必要があるので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。なお、督促状等が送られてきた場合は、督促状等は保管しておきましょう。
3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合については、こちらのページをご覧ください。
当事務所の相続放棄のサポート業務
- 必要書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 上申書の作成(相続開始から3か月以上経過の場合)
- 裁判所への申述書の提出代行
これまで説明してきたように、相続放棄には熟慮期間という3か月の期限があります。相続放棄が認められないと、場合によっては借金を背負ってしまうかもしれません。
相続が開始すると、葬儀や役所の手続きなどに追われると思います。そのような中で確実に相続放棄ができるか少しでもご不安な方は、当事務所にご相談ください。